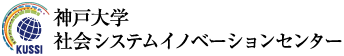構成メンバー
★はプロジェクトリーダー
★西村 和雄(計算社会科学研究センター・特命教授)
上東 貴志(計算社会科学研究センター・教授)
瀋 俊毅(経済経営研究所・教授)
岩佐 和道(経済経営研究所・教授)
胡 云芳(経済学研究科・教授)
井上 寛規(久留米大学経済学部・准教授)
加藤 五郎(California Polytechnic State University数学科・名誉教授)
岩木 直(産業技術総合研究所・研究グループ長)
八木 匡(同志社大学経済学部・教授)
稲川 三千代(聖ヨゼフ医療福祉センター・公認心理師)
Myles Suehiro(Hawaii Institute for Health and Healing・MD)
研究の目的と概要
バブル後、今日に至る我が国の長期停滞の深刻さは各種のデータに現れている。例えば、日本をシンガポールと比較すると、2023年の世界競争力ランキング(国際経営開発研究所)ではシンガポールが4位なのに対し、日本は35位である。これに対して、2024年の世界大学ランキングでは、シンガポール国立大学が19位なのに対して、日本の東京大学は29位、京都大学は55位であった。
教育投資の効果という点で、日本はシンガポールに遅れを取っている。実際、物的資本が投資によって価値を増加させることができるように、人間が持つ知識や技能も教育投資によって増加することが可能である。労働をその能力を含めて人的資本とみなし、マクロモデルに組み込んだ経済成長理論が提唱され、ポール・ローマーは2018年にノーベル経済学賞を受賞した。
本研究は、人的資本の経済における役割について、理論、実証の立場から文理融合的分析を行う。理論面では、非線形動学的手法を使って、海外の研究者と議論しながら、人的資本が経済成長や景気循環において果たす役割をマクロ経済学的に分析する。
実証面では、アンケート、実験、脳計測を用いながら、家庭教育や学校教育が人的資本の蓄積に果たす役割についてミクロ的に分析する。
以上の研究を社会実装する際には行動変容をもたらす要因にも注意を払う必要がある。更に、人々の認知タイプやモチベーションを理解した上で、個人毎に効果の高い指導法、学習法、育成法を検討することが望ましい。そこで、大阪市教育委員会との連携を図り、大阪市の児童・生徒の問題行動を減らし、学力を向上させる取り組みを進める。